幼いころから、私の懐には小汚いお馬さんが住んでいた。
それは誰にも見えない、私だけのお馬さんだった。手のひらほどの大きさで、ぼさぼさのたてがみを揺らしながら、私が悲しいときには優しく鼻先で突いて慰め、嬉しいときには小さなひづめを鳴らして喜んでくれた。
私はお馬さんと話しながら成長した。学校で友達とうまくいかなかったときも、親と衝突したときも、彼は静かにそばにいてくれた。世間の常識に囚われることなく、私だけの存在として。
しかし、大人になるにつれ、彼の姿を感じることが少なくなった。仕事に追われ、生活に追われ、周囲の期待に応えようと必死になっているうちに、ふと気がつくと、お馬さんはもう懐の中にはいなかった。
彼がいなくなったことに気づいたのは、ある冬の夜だった。
仕事で失敗し、恋人ともすれ違い、満員電車に揺られながら、私はふと自分の胸を押さえた。そこにいたはずのお馬さんの温もりはもう感じられない。ただ、冷たい風がコートの隙間から入り込むだけだった。
私は、お馬さんを失ってしまったのだろうか。
それとも、彼が必要のない大人になってしまったのだろうか。
その答えを探すために、私は久しぶりに夜の街を歩いた。人の少ない公園、昔よく遊んだ路地裏、小さな書店。どこにもお馬さんの姿はなかった。
途方に暮れていたとき、どこからか小さな声が聞こえた。
「忘れてはいないよね?」
驚いて振り返ると、そこには小さな光が揺らめいていた。
懐に手を入れると、温かいものが触れた。
私は思い出したのだ。お馬さんは、どこかに消えてしまったのではなく、ずっとそこにいたのだと。ただ、私が忙しさの中で、彼の存在を見ようとしなくなっていただけだったのだ。
そっと懐をなでると、小さな蹄の音が聞こえた気がした。
私は微笑んで、また歩き出した。
お馬さんは、これからも私の懐にいる。



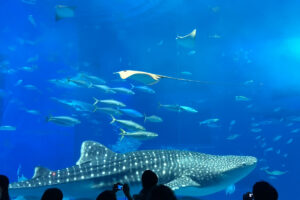








コメントを残す